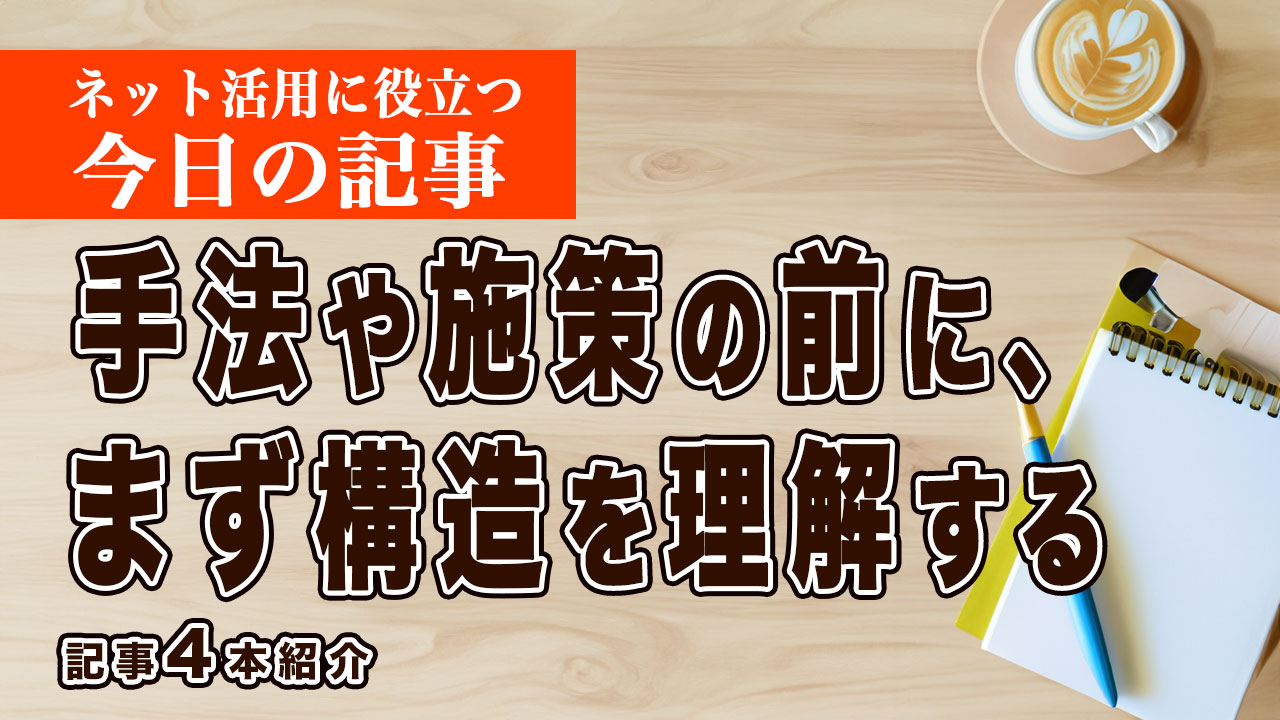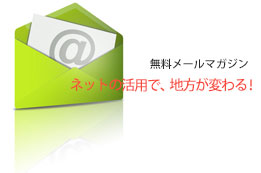Googleが提供しているAIツール「NotebookLM」を利用してポッドキャスト番組を作ってもらっいました。
ジャーナリストの小林雅一さんによる「グーグルの「会話生成AI」が超リアルでヤバい…これはChatGPTの登場時に匹敵する「衝撃」だ!」という記事を参考に、試しに私もポッドキャストの番組を作ってみました。結論から先に言いますと、ビックリ! のひと言です。
NotebookLM
NotebookLMは、Googleが開発した、「ドキュメントと対話できるAIツール」です。ドキュメントと対話ってなんのこっちゃ?と思う人もいるかと思いますが、特徴を紹介するとこんな感じです。
NotebookLMの主な特徴
- 様々な種類のファイルに対応
Googleドキュメント、PDF、テキストファイル、Googleスライド、ウェブサイトのURLなど、さまざまな種類のファイルをアップロードできる - AIが自動で内容を理解
アップロードしたドキュメントの内容をAIが自動的に読み込み、理解。そのため、長い文章を自分で読む必要なし - 質問に答えてくれる
ドキュメントの内容に関する質問をすると、AIがその質問に合った答えを生成してくれる - 要約を作成
長文のドキュメントを簡単に要約できる - 説明を生成
ドキュメントの内容をより詳しく説明することができる
そんなん、ChatGPT でも既存の生成AIサービスでもできるじゃん…?という思う方もいらっしゃるかと思いますが、その通りと言えばその通りです。
ChatGPT で画像も生成できるけど画像生成に特化した生成AIがあると一緒で、「ドキュメントを掘り下げる 」ことに特化した生成AIだと考えればいいと思います。
※どうでもいいことですが、私、最近頻繁に聞く「深掘り」という表現がどうもなじめなくて、あえて「掘り下げる」と表現しています…(^^;

NotebookLM の画面
ポッドキャスト番組を出力
さて、この NotebookLM の特徴「説明を生成」という範疇になりますが、「音声の概要」というツールがあります。NotebookLM では次のように紹介されています。
音声の概要は、ソースの主要なトピックの要約を、活発な「掘り下げた」ディスカッション形式にしたものです。これは試験運用中の機能です。
これは「Audio Overview」というもので、厳密にはポッドキャスト番組を作るものではなくて、取り込んだドキュメントの概要を音声ファイルにしてくれるというものです。例えば、長い報告書を全部読むのは大変な時、これをテキストとして短く要約したものを出力してもらう方法もありますが、これとは別に、概要を音声ファイルにしてもらってそれを移動中に聞くということが想定されています。
私も実際に「音声の概要」(=ポッドキャスト番組形式)を試してみました。
読み込んでもらう情報は、私が書いた下記のブログ記事。
ネット上にある4本の記事を取り上げて解説を加えているものです。
アルゴリズムの変遷とSNSへの影響など、ネット活用に役立つ記事をピックアップ #166
操作自体は簡単で、ブログ記事を読み込ませて、音声ファイルをダウンロードしただけ…。出力される音声は英語で、男女二人が番組形式で話しているものでした。
そして、それを聞いてみてビックリ!あらまぁ、なんと、驚きのひと言...
実際にどんなポッドキャスト番組になっているののか、翻訳字幕を加えましたので、ぜひ最後までご覧になってみてください。
※2025.4.30 追記
日本語で音声出力ができるようになりました。こちらの記事で紹介しています
2つの点で驚きました…
一つ目は、生成されている話し方や会話が自然なこと…。 現在ではAIが原稿を読んでくれるサービスがたくさん出ていますが、どんなに頑張ってもまだロポットっぽいところが残ってしまっていますが、このポッドキャスト番組はまったくそんなことを感じさせず、しかもただ原稿を読むという行為のレベルを超えて、自然な掛け合いまでされています。
二つ目は、ポッドキャスト番組の中で話されている内容です。
元になっている私のブログ記事と比較していただければわかりますが、記事に書かれている内容だけで番組が構成されているのではなくて、記事に掲載されている情報の周辺であったり、その背景となっている知識、さらには同じ物事を別な切り口で表現するなど、記事内容を膨らませて、かつ記事をまったく別な解釈でひっくり返すこともなく番組構成されています。これにはさすがに驚きました…。
ポッドキャストの会話の内容を文字にすると以下の通りです。
さて、あなたが送ってくれたアルゴリズムに関する記事について掘り下げていきます。オンラインで何が変わっているか、そしてそれがあなたにどう影響するか、非常に興味深い内容です。今回はビーチューという日本のウェブコンサルタントのブログ記事を取り上げます。彼らは、オンラインでの変化について非常に興味深い記事をいくつか取り上げていました。
本当に驚くほど速く変わっていますよね。
そうですね、オンラインでの情報の見え方や、ビジネスが人々とどのように繋がるか、すべてが非常に速く変わっています。そしてそのすべては、常に進化し続けているアルゴリズムのせいなんです。
さて、最初の記事ですが、アルゴリズムがどのようにシフトしているかについてです。以前は友達との繋がりが重視されていましたが、今は全く違います。
今では、見知らぬ人からでも注意を引くものが重要視されるようになっています。Facebookが家族や友達との繋がりを重視していた時代を覚えていますか?
今では大きな変化が起きています。繋がりからコンテンツへとシフトしているんです。もはやただオンラインにいるだけでは不十分で、アルゴリズムの注目をどう引くかを考えなければなりません。
これは全く新しい課題です。例えるなら、非常に騒がしい部屋の中で自分の声を聞かせるようなものです。でも、その部屋は猫の動画やターゲティング広告でいっぱいです。
少し考えてみてください。自分がSNSで何かを見た時、ブランドのことを知らない状態で実際にクリックすることってどれくらいありますか?
それは良い質問ですね。我々全員が考えるべき疑問です。そして、それはビーチューが指摘した2つ目の記事に繋がります。この記事は、企業がソーシャルメディアの専門家1人に頼るのではなく、全体のチームを構築する必要があると論じています。
つまり、製品と一緒に子犬の写真を投稿するだけではもう十分じゃないってことですか?
そう、全然足りないです。データ分析やコンテンツ作成、トレンド予測が必要なんです。もはやかわいいインスタグラムアカウントを持つだけでは不十分で、これらのプラットフォームを徹底的に理解する必要があります。アルゴリズムがどのように機能するのか、誰が自分のオーディエンスなのかを理解することが求められています。
ちょっと自分がオンラインで何をしているか考えてみてください。データ、コンテンツ、トレンド、これらすべてを自分一人でこなせますか?
とても大変です。今こそ、チームを考え始める時かもしれません。フリーランサーを数人でも雇ってサポートしてもらうのも一つの手です。
そうですね。そしてここでちょっと驚くかもしれないことがあります。AIを使った検索エンジンについて聞いたことがありますか? 質問に直接答えるものです。
ビーチューはPerplexityという例を挙げていますが、これが非常に興味深いんです。これらのAI検索エンジンは、もはやただ検索しているだけではなく、答えを提供してくれるんです。まるでインターネットの全知の神託のようです。
それは素晴らしいことのように聞こえますが、実は大きな問題もあります。この便利さ、すぐに答えを得られるということには、大きな影響があるかもしれません。
この記事では、2026年までに検索エンジンからのウェブサイトへのトラフィックが激減する可能性があると予測しています。つまり、ウェブサイトにアクセスする人が大幅に減少するかもしれないということです。
えっ、ちょっと待ってください。もしあなたのビジネスがウェブサイト訪問者に依存している場合、それはデジタルの終末が来るってことですか?
まあ、「終末」というのは少し誇張かもしれませんが、確かに時代に適応することの重要性を示していますよね。ここで登場するのが、生成型エンジン最適化(GEO)です。
SEOのようなものですが、さらに高度です。キーワードではなく、回答を最適化するんです。
え、どうやってそんなことが可能なんですか?
それは全く新しい世界です。もはや検索結果で上位に表示されるだけでは不十分で、ユーザーが求める最も直接的で、完全で、魅力的な回答を提供することが求められています。
そして、その答えは検索結果内にしっかりと表示されなければなりません。つまり、あなたはその分野のトップの専門家にならなければならないんです。ユーザーが最も信頼できる情報を提供する存在としてね。もうトリッキーなキーワードで隠れることはできません。常に全力で取り組む必要があります。
その通りです。そして、これが非常に重要な質問を生み出します。もしこれらのAI検索エンジンが本当に主流になった場合、企業は従来のSEOにこだわるべきなのでしょうか?それとも全く別のプラットフォーム、例えば人々が直接関わってくれるコミュニティを構築する方向にシフトするべきでしょうか?
実は、ウェブサイトのトラフィックが急激に減少するという統計を読んだとき、少し驚きました。
本当にそうですね。私たちはデジタル時代において消滅する運命なのでしょうか?「消滅」というのは言い過ぎかもしれませんが、確かに適応する時期が来ています。そしてその一つの方法が、強力で忠実なコミュニティを構築することです。検索エンジンがどうなろうと、コンテンツに直接関わってくれる人々がいるということが非常に重要です。
まさに戦う場所を選ぶということですね。AIの世界で存在感を示すために戦うか、それとも自分たちの小さな帝国を築くか。
いい例えですね。そして、正解は一つではないですよね。ビジネス、オーディエンス、そして目標によって異なります。別のアプローチに関していえば、ビーチューが言及していた最後の記事、東南アジアにおけるTikTokに関するものが、どれほど異なることがあり得るかを示しています。
ええ、TikTokはここでも非常に人気ですが、東南アジアではまったく違う使われ方をしているようです。そこではエンターテインメントやバイラルなトレンドだけでなく、日常生活やビジネス、さらには社会的な活動にも組み込まれているとのことです。つまり、ダンスチャレンジで100万ビューを獲得することよりも、コミュニティとリアルに繋がることが重視されているんです。
その通りです。そしてこれは、オンラインで成功しようとしている誰にとっても非常に重要なポイントを示しています。それは「多様性が鍵だ」ということです。異なる文化がどのようにこれらのプラットフォームを利用しているかを知ることで、新たなアイデアが生まれます。デスクチェアに座ったまま世界を旅しているようなものです。他の人々がこれらのツールをどのように使っているかを見るのは、本当に刺激になりますよ。
たとえ自分がTikTokをそのように使わなくても、オンライン世界は広大で、常に変化しており、そこには多くの多様性があることを思い出させてくれます。
私たちは「繋がり」から「コンテンツ」へ、ソーシャルメディアの専門家一人からチーム全体へ、SEOからGEOへと進んできました。そして最後に、ちょっとした東南アジアへの旅までしましたね。
本当に多くのことをカバーしましたね。でも、終わる前にもう一つ重要なことを話しておくべきです。
あ、クリフハンガーですね。今日のリスナーへのメッセージは何ですか?
私たちはアルゴリズムに適応することについて多く語ってきましたが、もしアルゴリズムが私たちの注意を引くものばかりを押し続けて、実際の繋がりを無視するようになったらどうなるでしょうか?オンラインコミュニティはどうなるのでしょうか?
そうですね。まるで巨大なデジタル都市を建設しているのに、公園やコミュニティセンターのような、その都市を住む価値のあるものにする要素を忘れているかのようです。
本当にその通りですね。これは、オンラインの世界を進む中で非常に考えさせられることです。この世界は常に変化しています。
最後にまとめると、オンラインの世界はかつてない速さで変わってきています。アルゴリズムがルールを決めていて、それにどう対応するかは私たち次第です。もしかすると、チームを作ることが必要かもしれませんし、オーディエンスと直接繋がる新しい方法を見つけることが重要かもしれません。そして、時には立ち止まって、リアルな繋がりを見失わないようにすることも大切です。
アルゴリズムやAIについて語ってきましたが、最後にとても人間らしい考えで締めくくります。
それでは、これで終わりです。ご参加ありがとうございました。また次回お会いしましょう。
これが日本語出力にも対応してくれたらどんなにうれしいか…と思う一方で、
もしそうなった時にはきっと多くの人が利用するでしょうから、その時、ポッドキャスト番組を聞く人はどんな気に持ちになるのだろう…?とも…
ニュースや最新情報という、単なる情報を追うだけのものならまだしも、
生成AIで簡単に作られた…ということは別に「その人でなくてもいい」ということを意味しますので、その場合に「その人ならではの価値」をどのように担保していったらいいのだろうかと。
ご興味ある方はぜひ、NotebookLM を覗いてみてくださいね。
次回をお楽しみに!
こちらの記事もおすすめ!
ネット活用のヒントを配信中!
ネット活用のヒントを check!!
- 地方・中小企業の皆様 …… 今、目の前にあるチャンス! & 売れる仕組み作り
- 自治体サイト担当者様 …… 自治体ホームページの課題と可能性を知る
- 観光に関わる皆様 …… ネット活用の "もったいない!" 事例を紹介