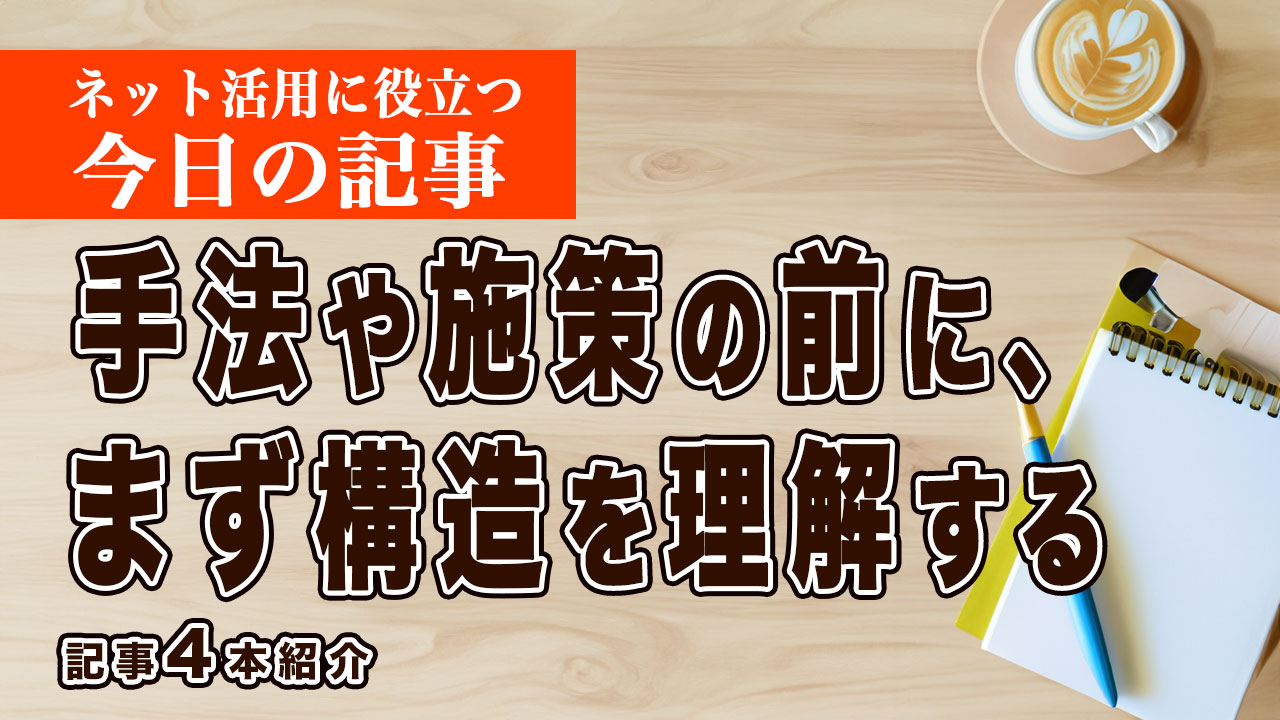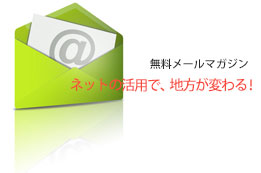地方や中小企業のネット活用に役立つ記事をピックアップして紹介しています。
みなさんの仕事の現場でお役立てください
今回は以下の4本です
- サイトの表示、待てるのは10秒まで
- 「AIに任せる検索」Agentic Search?
- Facebookの動画は、すべて「リール」に
- インスタ画像の推奨サイズ
サイトの表示、待てるのは10秒まで
4割以上がWEBサイトの読み込みの遅さを経験 離脱経験は約4割、離脱の分かれ道は「10秒以内の表示」 離脱しやすいジャンルは「ニュース、メディアサイト」「EC」「ブログ、まとめサイト」(MMD研究所)
今回ご紹介するのは、MMD研究所が実施した「WEBサイトの表示に関する調査」。
全国の男女約1万人を対象に、スマホでサイトを見たときに「読み込みが遅い」と感じた経験や、そのときの行動について調査しています。
注目すべきなのは、「表示が遅い」と感じたユーザーの約4割がその時点で離脱しているという点です。また、「どれくらいの時間なら我慢できるか」という問いには、71%が10秒以内と答えており、中でも4〜5秒が最も多くなっています。つまり、5秒以上かかると離脱したくなり、10秒が限度ということが言えそうです。
さらに、調査では、離脱しやすいジャンルとしてニュース・ECサイト・まとめブログが挙げられています。
中小企業にとっても、これは他人事ではありません。
せっかく興味を持って訪問してくれた人が、「表示が遅い」という理由だけで離れていくのは本当にもったいないことです。サイトの中身・見た目だけでなく、表示スピードの改善も頭の片隅に置いておく必要がありそうです。とくにスマホでの表示チェックや、重たい画像・動画の扱いには注意したいところです。
「内容がよければ見てくれるだろう」ではなく、「すぐ見られなければ中身も見てもらえない」という前提で、サイト運営を考える必要がありそうてす。Check it!
「AIに任せる検索」Agentic Search?
“聞く”から“任せる”へ 「Agentic Search」が起こす、検索体験の転換とファネルの崩壊(MarkeZine)
このサイトでも何度も取り上げていますが、いま、検索のあり方が根本から変わろうとしています。
今回の記事で紹介されているのは、今、まさに始まり出した「Agentic Search(エージェンティック・サーチ)」という新しい検索体験についてです。
これまでの検索は、「ユーザーがキーワードを入力して、出てきた候補を自分で選ぶ」というものでした。ですがこれからは、「AIに○○したいと伝えるだけで、AIが調べて、比較して、提案して、必要なら予約や購入までやってくれる」という、利用者にとっては夢のような時代です。
まさに、「聞く」から「(AIに)任せる」への大転換です。
そんな夢のような時代が「これから来る」のではなく、「すでに始まっちゃった…」ということが重要なポイントの一つです。
記事では、これらが急速に進んでいる背景には次の4つがあると紹介しています。
- LLM(GPT-4、Claudeなど)の高性能化
- マルチモーダルAIの進化(画像・音声も理解)
- 企業導入の進展(例:Blue Prism調査)
- 「比較したくない・任せたい」というユーザー心理
また、記事では、Google GeminiやPerplexityなどの最新サービスを紹介しながら、この変化がSEO、サイト設計、マーケティング全体にどんな影響を与えるかが解説されています。
記事では4つのポイントが紹介されていますが、特に注目すべきは、「AIに選ばれること」が重要になるという点です。これまでのように、「検索上位に出る」ことがゴールではなくなります。
ユーザーが検索する前に、AIが最適だと判断して、自動で企業や商品を提案するようになるため、「AIが理解しやすく、信頼できる情報」をどう提供しているかが問われるということです。
と、このような表現をすると、どこか「IT専門・最先端の大企業の話」というふうに思われてしまうのですが、そうではありません。確かに、このような「仕組み」を構築しサービス提供してくるのはGoogleのような大企業ですし、これらのサービスを最初に利用するのも大企業です。ですがですが、これらのサービスが出回ることによって影響を受けるのは我々中小企業に他なりません。
私たち中小企業は、自らがサービスを利用するのではなくとも、これらのサービスが世に出はじめることによって「風に舞うこの葉」のごとく、否応なくその影響下で右往左往せざるを得ません。
(この後の3本目・4本目の記事も、まさに同じことです)
まずは、今、地方・中小企業が情報発信や集客をしている「足元の環境」が大きく変わり始めているという事実をしっかりと認識していただくこと、そして、これからは「お客さんに選んでもらう」だけでなく「AIにも選んでもらう」ということ考えながら、情報発信を見直していくことが必要になります。
そんな大きな視線で、ぜひご一読ください。Check it!
Facebookの動画は、すべて「リール」に
Facebookが、動画の投稿方法を大きく変えようとしていることが紹介されています。
これまでFacebookでは、「リール(Reels)」と「(通常の)動画」は別々の形式で投稿していましたが、今後はすべての動画が自動的にリールとして扱われるようになるとのこと。簡単に言うと、これまでの「通常の動画投稿」というものがなくなるということです。
記事ではその背景として、FacebookではReelsが最も高いエンゲージメントを生み出しており、ユーザーのアプリ内滞在時間の増加に大きく貢献していることを指摘しています。言ってみれば、リール動画の方が Facebookにとっては儲かる ということです。d(^_^)
さて、この変化について、私たち中小企業は2つのことを理解しておく必要があります。
一つ目は、今回消滅する「通常の動画」と「リール動画」はそもそも何が違っているのかということ。もともと Facebookは「友達」や「フォローした人」の投稿が見えるというのが基本形式でした。この基本形式の中で「今日、こんな体験をした♪」と動画で見せるのが「通常の動画」です。動画を見るのは「友達」や「フォローした人」で、動画表示の起点は、友達やフォローという「人とのつながり」(=ソーシャルネットワーク)になっていました。
一方で、「リール動画」は、TikTok が採用した表示構造で、「友達」や「フォローしているか」には関係なく、アルゴリズムがおもしろいと判断したものを、それに興味がありそうな人に表示させるという仕組みです。動画表示の起点に「人とのつながり」はなく、単に、アルゴリズムによる判断があるだけです。
今回、Facebookが「通常の動画」をやめて「リール動画」に全面移行するということは、Facebook がかつてのようなソーシャルネットワークを土台にした SNS ではもはやない、ということに他なりません。これまでの「友達やフォローした相手の投稿が見える」SNSの形から、アルゴリズムが「面白い」と判断した動画をどんどん見せる、「おすすめ動画中心」のプラットフォームへの移行です。TikTokと同じように、「知らない人の動画でも興味があれば見られる」環境に、Facebookも完全にシフトするということです。
二つ目は、Facebookを利用・投稿する我々の立ち位置です。
すでに Facebook はおじさん・おばさんのメディアになってしまっているわけですが…(^^;、その多くが、投稿を「友達・フォロワーが見る」という前提で利用しているはずです。そこにはもしかしたら、友達やフォロワーだけが共有する前提のようなものがあるかもしれません。ですが、Facebookはもはや閉じた空間ではなく、意図せずにアルゴリズムによって世界中のユーザーに情報が表示される空間に変化しています。そのことを理解した上で利用することが求められます。
ところで、中小企業にとって、この変化は大きなチャンスでもあります。
友達の数やフォロワーの多さに関係なく、「面白い」「役に立つ」動画であれば、アルゴリズムが見せたい相手に自動で届けてくれる時代になってきているわけですから。
(インスタグラムや TikTok の利用者にとっては慣れた世界だと思います)
つまり、フォロワーが少なくても、一本の動画がきっかけで多くの人に届く可能性があるということです。
ソーシャルネットワークは、もはや「友達とつながる場所」だけではありません。AIによる発見が中心となる「動画メディア」としての側面が強まっています。自社の魅力や価値を、動画でどう伝えるか。今こそ、動画発信の方法を見直すタイミングかもしれません。
ぜひご一読ください。Check it!
インスタ画像の推奨サイズ
【最新版】インスタ投稿の画像サイズは「3:4」でなく「4:5」!? サイズ変更への対応方法と投稿戦略(Web担)
2025年に入り、Instagramのプロフィールグリッド(投稿一覧)での画像の表示比率が、これまでの正方形(1:1)から縦長(3:4)に変更されました。この変更により、これまで正方形に合わせてデザインしていた投稿が左右で切れてしまったり、見栄えが崩れてしまっている人もいるかと思います。実は、私もその一人です…(^^;。
記事では、Instagramのフィード投稿サイズ変更に関する最新情報が紹介されています。
特に注意すべきポイントは、「画像サイズの推奨値」と「余白の設計」とのこと。
Metaの公式発表によると、これからの推奨サイズは1080×1350px(4:5)。ただし、プロフィール一覧ではやや縦長の3:4比率で表示されるため、画像の左右と上下が少し見切れるという特性があります。
そこで大切なのは、画像の中心に重要な情報を置くこと。タイトルや商品写真、キャンペーンの文字情報などを中央寄せにしておけば、どの表示形式でも内容がしっかり伝わるようになるとのこと。
ちなみに、これらのサイズ変更は、Instagramが縦長コンテンツを重視し、視認性や没入感を高めていく戦略の一環で、リール動画や縦長写真が中心になりつつある中で、投稿もその流れに合わせて変化したと解説されています。
私たち中小企業は、右といわれれば右、左といわれれば左へと対応していく他ありません。(いや、決して投げやりで言っているわけでありません…)
せっかく作った投稿が「伝わりにくい」「切れて見える」状態では、情報発信の効果が大きく損われてしまいます。ちょっとしたサイズ調整や配置の見直しで、印象や伝わり方が大きく変わります。投稿がきちんと「見える」「伝わる」こと。その基本をおさえるためにも、面倒ですが一つ一つ調整していくことが重要です。
やり方は記事に掲載されていますので、ぜひご一読ください。Check it!
次回をお楽しみに!
こちらの記事もおすすめ!
ネット活用のヒントを配信中!
ネット活用のヒントを check!!
- 地方・中小企業の皆様 …… 今、目の前にあるチャンス! & 売れる仕組み作り
- 自治体サイト担当者様 …… 自治体ホームページの課題と可能性を知る
- 観光に関わる皆様 …… ネット活用の "もったいない!" 事例を紹介