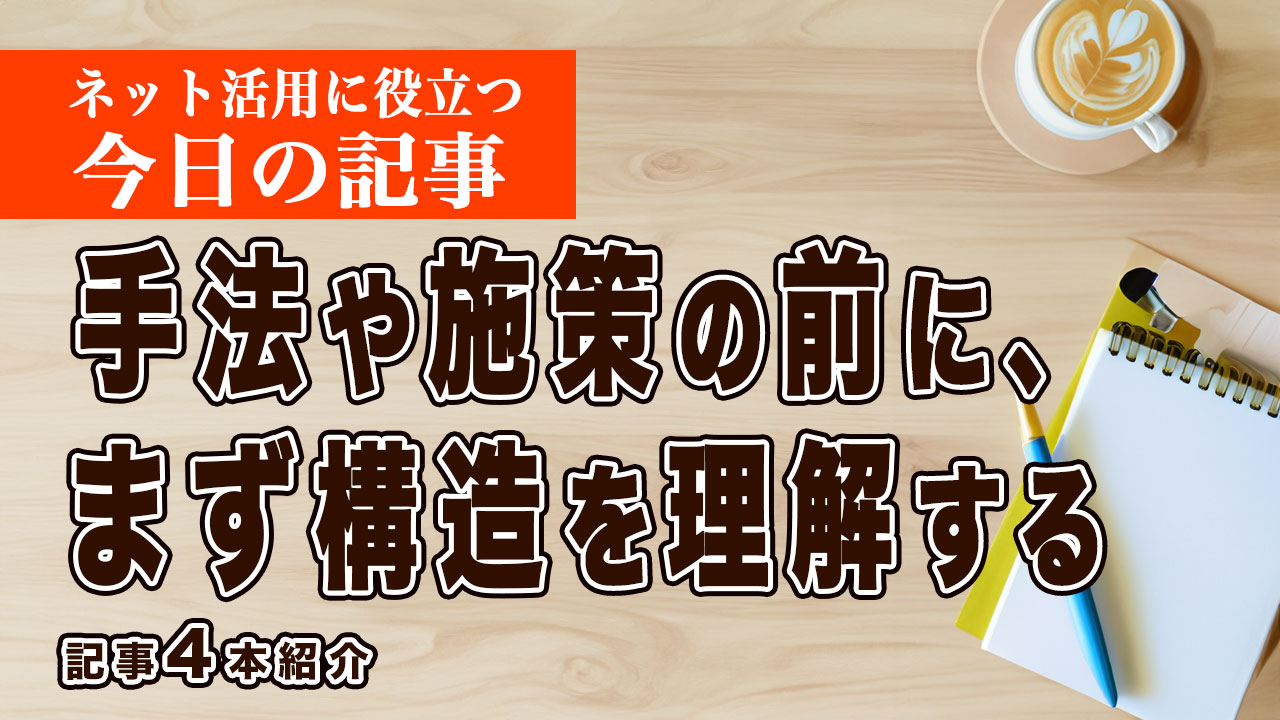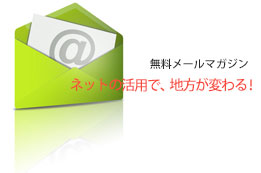地方や中小企業のネット活用に役立つ記事をピックアップして紹介しています。
みなさんの仕事の現場でお役立てください
今回は以下の4本です
- 検索結果、何ページ見る?
- 中小企業のデジタルマーケ 実施はわずか 6.1%
- 世代別のSNS利用状況
- 「SNSネイティブ」の消費行動から学ぶ
検索結果、何ページ見る?
【検索結果、どこまで見る?】85.6%が、3ページ目までで見るのをやめている!(NEXER)
検索をするとき、人は一体どこまで結果を見るのか。
そんな素朴だけど、意外と大事なテーマに関して、全国の男女500人を対象にした調査結果が紹介されています。
記事では、「検索結果をどこまで見るか?」「見つからなかった場合にどうするか?」「検索順位で信頼度に差を感じるか?」などについて、具体的な数字と理由が掲載されています。
調査によると、85.6%の人が検索結果の3ページ目までで見るのをやめているとのこと。
また、情報が見つからなかった場合は、66.8%の人が検索キーワードを変えると答えていて、検索を繰り返す中で納得できる情報にたどり着こうとしている様子がうかがえます。
さらに、約半数の人が「検索順位によって情報の信頼度に違いを感じる」とも答えていて、検索上位にあることがある程度の信頼の指標として受け取られているということも見えてきます。一方で、約半数の人は「違いを感じない」としており、ここは真っ二つの傾向に分かれています。それぞれ、なぜそのように思うのかも紹介されていますので、詳しくは記事をご覧ください。
地方の中小企業にとってのこの記事のポイントは、まずは
- 85.6%の人が検索結果の3ページ目までで見るのをやめている
- 情報が見つからなかった場合は、検索キーワードを変えて調べ直す
という事実です。そして「検索結果の3ページ以内に出てこなければ、存在しないのと同じ」という現実がある、ということです。「検索」を通してお客様に自社のことを「見つけてもらう」「知ってもらう」のであれば、この基準があることを知っておく必要があります。
※ちなみに、「見つけてもらう」「知ってもらう」方法は、ネットを活用する場合であっても「検索」以外にも色々な方法があります。どの方法がいいのかは、扱うサービスであったり、競合における自社の立ち位置によっても異なります。d(^_^)
なお、この調査記事はSEO会社による監修のもとで書かれていますので、調査結果の最後に「検索上位にある情報がいかに重視されているかがわかる」とまとめられていますが、調査結果のデータからすると少し恣意的な印象もあります。一方で「3ページ目までは見てくれる人がいる」という事実が分かったことの方が情報発信側にとってはありがたいヒントになるかと思います。
加えて、この「ピックアップ記事」で何度も書いているように「AI検索」がこれから主流になる中で、ページを「見に行く」のではなくAIに「探してきてもらう」という体験が中心になることが予想されます。その点で、この調査結果とはまた違う景色に広がってくることになると思われます。
検索行動を知るうえで非常に参考になる調査記事です。ぜひご一読ください。Check it!
中小企業のデジタルマーケ 実施はわずか 6.1%
ホームページ作成ツール「ペライチ」が実施した、中小企業のデジタルマーケティングに関する調査結果です。
調査は、同じ質問項目を、「ペライチ」の利用者と、利用していない中小企業とを比較する形で行われています。
調査によると、ペライチを利用していない中小企業では、
- デジタルマーケティングに取り組んでいるのはわずか 6.1%
- オンライン営業や商談の実施率は1割強
- WebサイトやECの改善更新は3割弱の実施
とのこと。
もう一度書きますね。
中小企業のうち、デジタルマーケティングに取り組んでいるのは、わずか 6.1%!
圧倒的多く、いやいや、ほとんどの会社がデジタル(≒ネット) を利用した集客や顧客サポートを実施していない…ということがわかります。
また課題としては、Webサイト運用の「更新や変更が手間」、顧客データの「分析が煩雑」、レポート作成での「データ解釈の難しさ」など、人手不足や知識不足に起因する困難さが数多くあがっています。
地方の中小企業にとって、この調査から何が言えるのでしょうか?
まず何よりも、「デジタル化に取り組んでいる企業が、まだ1割程度しかいない」という現実…。もはや、やっていないこと自体を責められるような状況ではないということです。むしろ、これから始める(だろう)会社の方が多数派であり、着手すること自体が差別化になる段階だということです。
さらに、私には次のように見えます。
インスタグラムや X、YouTube・TikTok で「情報発信」をしている中小企業はもう少し多いはずです。このことと今回の調査結果を合わせて考えると、SNS で情報発信はするが、デジタルを利用した集客やデータの活用といった領域にはまったく手がついていないことがうかがえます。別な見方をすれば、集客やお客様とのコミュニケーションという「全体的な仕組み」は一切考えずに、ただ SNSで情報発信だけしている、という言い方もできるかもしれません。調査結果を見れば、これからデジタルに取り組もうとしている方にとって「あ、自分だけじゃないんだ」と思える安心材料にもなるかもしれませんが、安心するのではなく、ぜひ「チャンス」なのだと捉えていただきたいと思います。
なお、この調査結果は、「ペライチを利用するとデジタルマーケティングの取り組みが加速する」と、因果関係が一部逆に見えてしまう可能性もありますので注意が必要です。デジタルに前向きな人がペライチのサービスを利用しているというのが正しい因果関係です。
ですが、実際に数字として、どこでつまずきやすいか、どんな壁があるのかを可視化してくれた点は、この調査の大きな意義です。「更新が面倒」「わからないから手が出ない」、そんな声が可視化されているからこそ、私たち支援側や地域全体でのサポートの必要性が見えてきます。
そんな中小企業の現場が垣間見える調査結果をぜひご一読ください。Check it!
世代別のSNS利用状況
【2025年最新!世代別のSNS利用状況とは】インフルエンサー投稿の影響を受けやすい世代や購買影響のリアルを徹底調査!(PRIZMA)
今やSNSは、どの世代にとっても身近な情報源になっていますが、「誰が」「どのSNSを」「どんな目的で使っているか」は、実は世代によって大きく違います。
記事では、Z世代(15~27歳)、Y世代(28~42歳)、X世代(43~58歳)を対象に、SNSの使い方や、どんな情報に影響を受けているのかが紹介されています。
調査結果によると、情報源としてのSNS利用率は全体で84.6%。
特にZ世代(15~27歳)は9割近くがSNS中心で情報収集しており、YouTube・Instagram・TikTokなど、「流れてくる情報」に自然と触れるスタイルが主流です。
一方でX世代(43~58歳)は、テレビやニュースサイト、企業の公式Webなど、信頼性や網羅性を重視した情報源が多く、世代ごとに「入口となるメディア」がまったく違うことが明らかになっています。
また、年収別の傾向も興味深く、TikTokは年収200万円未満層に多く、Facebookは年収500万円以上層での利用がやや高い傾向が出ています。
これから、どの世代にも同じ情報を同じ伝え方で届けるのは、もう通用しない時代になっているということがわかります。世代や所得層ごとのSNSの使われ方が、ここまでくっきり違うことを数字で見せてくれる、とても実用的な調査です。
では、この調査から地方の中小企業にとって何が読み取れるでしょうか。
一言でいえば、「誰に届けるかによって、使うSNSや言葉を変える必要がある」ということです。
例えば、若い層を狙いたいならTikTokやInstagram、比較的高年齢層や所得層ならYouTubeやFacebook、さらに、Z世代は「推し」やインフルエンサーから影響を受けやすいのに対して、X世代は「自分で調べて判断する」傾向が強いなどなど…ここをしっかりと考えないといけないということですね。d(^_^)
自社の情報発信やSNS活用を見直す上で、ヒントが詰まった調査結果、ぜひご一読ください。
さらに詳しい調査結果は下記からダウンロードできるそうです。ご興味ある方はあわせてどうぞ。Check it!
「SNSネイティブ」の消費行動から学ぶ
SNSネイティブ世代の消費行動からひもとく、メディアと広告コミュニケーションの未来(電通報)
記事では、SNSネイティブ世代(いわゆるZ世代)の消費行動の変化と、これからの広告やお店のあり方について紹介されています。
記事の中で特に注目されていたのが、実店舗の役割の変化。
これまでは「商品を売る場所」だったお店が、これからは「体験を提供する場所」に変わっていくという話が出てきます。
例えば、お店の中で自由に写真を撮ってSNSに投稿できるようにすると、その写真が拡散されて、お店の知名度が上がったり、来店のきっかけになったりするそうで、いまや、SNSがリアル店舗のプロモーションを担う時代だということです。
また、広告についても「効率よく伝えるだけでは足りない」という話が出てきます。SNSネイティブは、スキマ時間にスマホを見ながら情報を得ていて、広告もその合間に「ちょっと気になる」「何これ?」と思えるような仕掛けが求められているそうです。
記事自体は、どちらかというと大企業に関する内容なのですが、見方を変えると地方の中小企業にとってもかなり重要なヒントが詰まっています。
例えば、記事に登場する
- お店の「撮影OKな雰囲気」をつくるだけでも、SNS拡散のきっかけになる
- 商品名ではなく「体験」で覚えてもらうと、「また行きたい」に変わる
- 「最近ちょくちょく見るよね」と思われる接点を、SNSや店頭など複数つくると、購買の後押しになる
などは、そのまま中小企業でも実践できる内容です。
「ものを売る」から「体験を届ける」へ。そんな時代の変化を見つめ直すきっかけとして、ぜひ、自分の会社・お店だったらどこにアタはまりそうかを考えながら読んでみてください。d(^_^) Check it!
次回をお楽しみに!
こちらの記事もおすすめ!
ネット活用のヒントを配信中!
ネット活用のヒントを check!!
- 地方・中小企業の皆様 …… 今、目の前にあるチャンス! & 売れる仕組み作り
- 自治体サイト担当者様 …… 自治体ホームページの課題と可能性を知る
- 観光に関わる皆様 …… ネット活用の "もったいない!" 事例を紹介