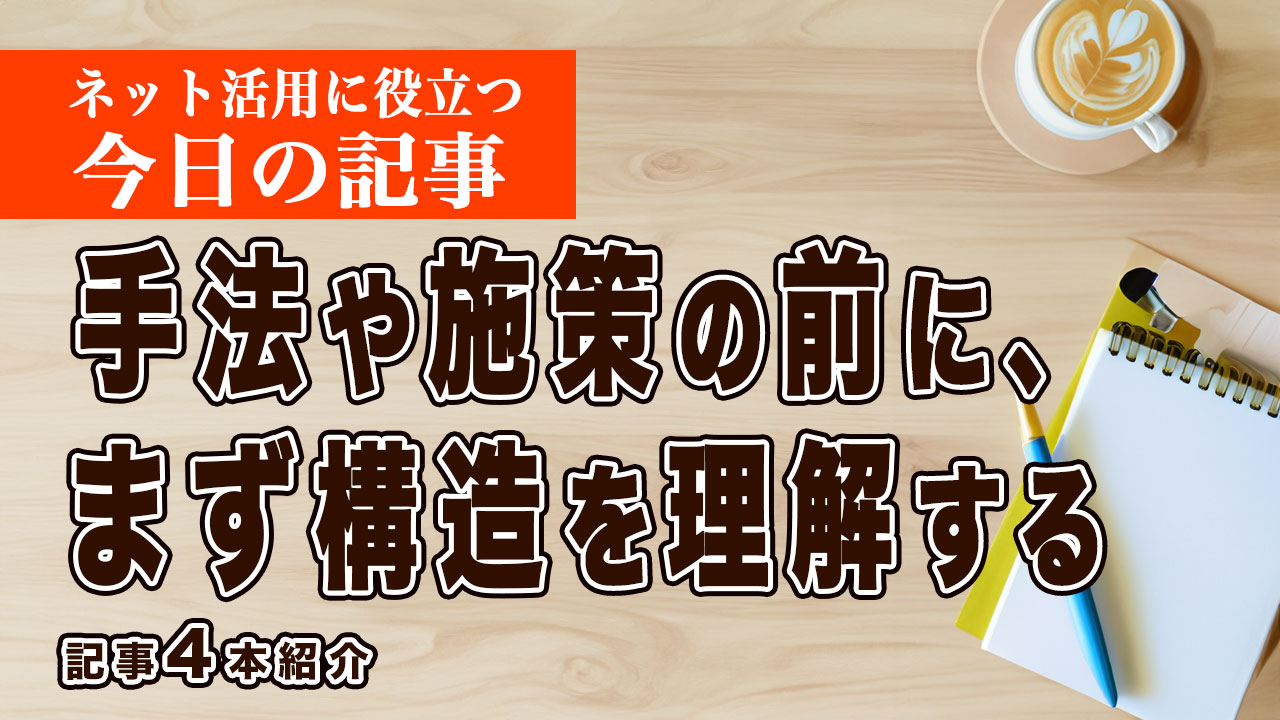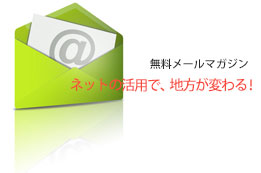地方や中小企業のネット活用に役立つ記事をピックアップして紹介しています。
みなさんの仕事の現場でお役立てください
今回は以下の4本です
- AIでSEOは終わる?
- 中小企業の生成AI活用
- アメリカ中小のSNS事情に学ぶ
- ECを成功させるためのヒント
AIでSEOは終わる?
「AIでSEOは終わるのか?」―経営・現場レベルでリアルな対応方針を検討してみた!(アドタイ)
AI検索が普及していく中で、「もうSEOは終わるのでは?」という声が現場の間でも話題になっています。
記事では、SEO関係者へのヒアリングをもとに、AI検索とSEOの今後について考察されて丁寧に解説してくれています。
注目すべきは、AIによる影響が2つの形で現れているという点です。
- 1つは、Google検索に表示される「AI OverViews」によって、簡単な質問への検索流入が減っていること。
いわゆる「ゼロクリック」ということです - もう1つは、ChatGPTやPerplexityなどのAI検索で情報収集が完結し、検索されないまま終わるケースが増えていることです。
※このことは、私のこれまでの「ピックアップ」でも紹介していることですね d(^_^)
記事ではこれらについて、SEO業界関係者へのヒアリングから、現在のところ影響が大きいのは「〜とは」「〜の理由」などのシンプルな質問で、売上や問い合わせに直結する検索には大きな影響は出ていないと報告されています。
※スルッとこのように表現していますが、そもそも「売上や問い合わせに直結する検索」とそうでない検索とがあるという事実を知っていることが、まずは大きなポイント。d(^_^)
また、AI検索の情報源は、実はGoogleやBingの検索結果なので、通常のSEO対策は引き続き有効だとも説明されています。
※補足の説明をすると、ChatGPTはBingの検索情報を利用していますし、GeminはGoogleの検索情報を利用しています
さらに詳しい解説は記事をご覧いただきたいと思いますが、中小企業にとってのポイントは、「AI対策のために特別なことをする必要はないが、基本のSEOをより丁寧にやる必要がある」ということ。そして、AI検索の時代でも評価されるのは、自社ならではの一次情報や信頼できる実名によるコンテンツということになりそうです。
細かいところでは私の考えと少し違いますが、大枠では私の考え方に近い内容です。
ぜひご一読ください。Check it!
中小企業の生成AI活用
完全ノーコードで、紙書類のスキャンデータから必要な情報だけを抽出する生成AIアプリを5分で作ってみた(@umapyoi)
プログラムが書けなくても利用できる無料ノーコードツールを利用して、スキャンデータから必要な情報だけを抽出する生成AIアプリを作った様子が紹介されています。
紙に印刷されている書類から一部を抜き出してエクセルなどにまとめていく作業は、かつてはとても手間がかかる作業でした。
「でした」と過去形で書いてしまいますが、実際には、今現在も、多くの方が手作業でされている可能性が高いです…。
中小企業の皆さんに記事をご覧いただきたいポイントは2つあります。
一つは、これら手間がかかる作業が、生成AIを活用することで簡単にできるようになるということと。
もう一つは、生成AIを利用したその仕組み自体も、プログラムが書けなくても作れる時代になってきた、ということです。
ここ数年で、二重に大きな変化が起きているということを理解しておく必要があります。d(^_^)
生成AIによる業務改善は決して大企業だけのものではありません。
記事では細かく作り方が紹介されていますが、ひとまず作り方を覚える必要はありません。重要なのは「中小企業でもこういう方法があるんだ」ということを知ること。まずは、今、私たちが立っている場所をぜひ知っていただきたいと思います。Check it!
アメリカ中小のSNS事情に学ぶ
バズらないモノは存在しないのも同然、コンテンツを内製する米中小企業の実態(Forbes Japan)
アメリカの中小企業がSNSにより積極的に取り組んでいる様子が紹介されています。
記事で紹介されている、従業員数500人以下の米国600社の経営者を対象にした調査の中から一部を取り上げると、
過去1年間のコンテンツの取り扱い
- コンテンツの制作を開始:20%
- コンテンツを制作しており、予算を増額:42%
- コンテンツを制作しているが、予算は増額していない:19%
- コンテンツは制作していない。将来は制作予定:11%
- コンテンツは制作していない。将来その予定もない:8%
コンテンツの制作担当者
- 専任の内製チームあり:33%
- 担当者が内製:38%
- 他業務と兼任:25%
- 外注:4%
課題
- コンテンツ制作の継続性やトレンド対応に苦戦:54%
- リソースの確保が難しい:56%
- SNS運用の優先順位付けが困難:56%
その他の調査結果を含めて、米国中小企業の取り組みの実態は記事をご覧いただきたいと思います。
この記事における、私たち日本の中小企業にとってのポイントは次の2つかと思います。
一つ目は、記事タイトルにある「SNSでバズらないものは、世の中に存在していないのも同然」という表現。
これは、調査結果をまとめているフォーブスの "釣り" というか、誇張タイトルです。実際の調査結果からは、ソーシャルメディアがビジネスにとって重要であり活用が進んでいることはわかりますが、バズらないと存在しないのと同じという明確な意識があるわけではありません。そこは注意が必要ですし、タイトルに簡単に持っていかれないようにしないといけません。d(^_^)
二つ目は、私たち(日本の)中小企業は SNS をはじめ情報発信を一生懸命頑張っていますが、海外でも同じような姿があるのだという事実です。調査結果を見ていただくと、人員や大切の確保や、目まぐるしく変わるトレンド変更への対応、コンテンツ制作への苦慮といったことは海外の中小企業でも同じなんだということがわかります。
海外でも同じように現場での戦いがあることがわかる記事ですので、ぜひご一読ください。Check it!
記事のもとになっていく調査結果はこちらです。
VERIZON BUSINESS’ 6TH ANNUAL STATE OF SMALL BUSINESS SURVEY
ECを成功させるためのヒント
BtoB企業・アネスト岩田が“BtoC”で直販経験を積んだ理由とは 挑戦の裏側に迫る(ECzine)
エアーブラシのEC販売を進めていった舞台裏が紹介されています。
集客に工夫をしたり、代理店では販売しない自社EC専売商品にしたりと、課題を次々に解決しながら売り上げを増やしていった様子がわかります。
情報発信もECサイトでの販売も、最初の予想通りにうまくいくものでは決してありません。多くが「思った通りの結果が出ない」という状況から、あれこれ一つ一つ課題を解決していって、結果的に売り上げが増加するという道のりとなります。そういう意味では「こうすれば必ずうまくいく!」という単純なことではなく、「こうやったらうまく行った」「こうやったけどダメだった」という他社の事例から、(そのまま成功事例をまねるのではなく)その背後にある「考え方」を自社で試してみることがポイントになってきます。
そんな事例がいっぱいつまった記事です。後半の BtoBのEC販売への挑戦と合わせてぜひご覧ください。Check it!
次回をお楽しみに!
こちらの記事もおすすめ!
ネット活用のヒントを配信中!
ネット活用のヒントを check!!
- 地方・中小企業の皆様 …… 今、目の前にあるチャンス! & 売れる仕組み作り
- 自治体サイト担当者様 …… 自治体ホームページの課題と可能性を知る
- 観光に関わる皆様 …… ネット活用の "もったいない!" 事例を紹介