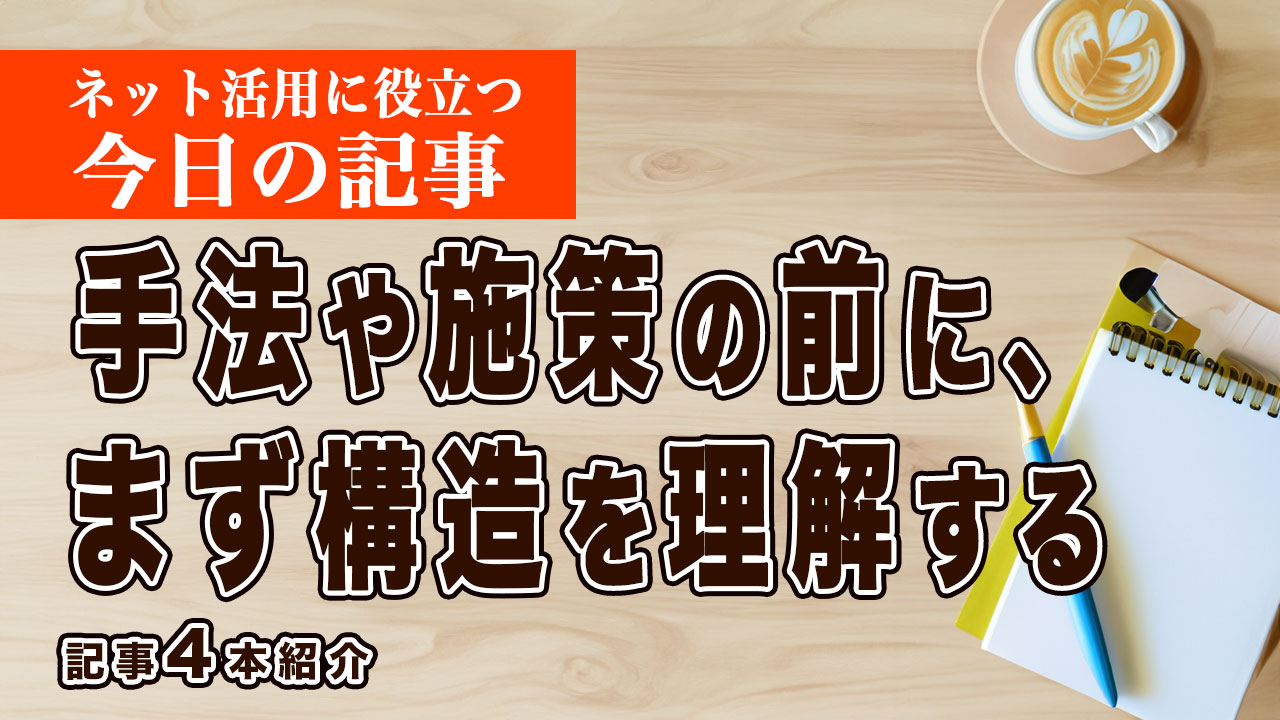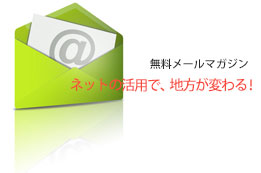地方や中小企業のネット活用に役立つ記事をピックアップして紹介しています。
みなさんの仕事の現場でお役立てください
今回は以下の4本です
- 8割がダウンロード資料に「がっかり」
- ChatGPTの社内活用、はじめる前に知っておきたいこと
- 生成AIと付き合うコツ
- AI検索は「順位」よりも「Retrieval」
8割がダウンロード資料に「がっかり」
【BtoB企業|DL後の失望】8割以上が、個人情報と引き換えのダウンロードコンテンツに「がっかり」(IDEATECH)
BtoB企業のマーケ施策で定番となっている「ホワイトペーパーのダウンロード」に関する調査結果です。
約8割のユーザーが「資料をダウンロードしてがっかりした経験がある」とのこと。「中身が薄い」「知っていることばかり」「営業臭が強い」といった、内容の期待外れが主な原因です。
一方で、質の高いコンテンツに出会った場合、「その企業への発注意欲が高まる」と答えた人は83.4%もありました。
ホワイトペーパ提供側からすると、資料を作るのに手間をかけずに(現場として手前をかけたくない)見込み客の情報が取得できるのであればそれに越したことはない…と「提供側都合」の資料になりがちです。時に単なる営業資料に過ぎない場合もあります。この意識が「ダウンロードする側」と大きく乖離してしまっていることが、これらの調査結果の根本的な原因です。
特に、「ホワイトペーパー / 資料ダウンロード = リスト取り」という、手法的な側面ばかり意識してしまっていると陥る可能性が高くなります。
自社のことを(都合よく)伝えるツールとしてではなく、その資料を読んだ人が抱く心理的な側面(例えば、信頼)までも含めてダウンロード資料の提供だということを私たちは理解しておく必要があります。相手の期待に応える「本気の情報提供」が求められているということです。
そのような視点で調査結果をぜひご一読ください。Check it!
ChatGPTの社内活用、はじめる前に知っておきたいこと
ChatGPTでの業務改善に失敗する前に読むnote(うめもと)
生成AIの導入は、個人で利用するのと、組織で利用するのとでは、導入の難易度に違いがあります。簡単に言えば、個人は比較的簡単ですが、これが組織となると急に難易度があがります。
この記事では、ChatGPTなどの生成AIを業務改善に活用する際、ありがちなつまずきとその解決策が実例ベースで紹介されていて、(個人ではなく)組織としての生成AIの導入の参考になります。
特に注目すべきは、「小さく始めて早く成果を出すこと」。完璧を目指すのではなく、まずは生成AIに任せられる業務を見つけ、早く効果を実感することで、社内の推進力が高まるとのこと。また、「プロンプト共通化」や「使ってみて体験させる」など、現場での定着に向けた具体策も解説されていて勉強になります。
AI導入は決して大企業だけのものではありません。むしろ、中小企業こそがその恩恵によって大企業にも負けないパワーを発揮するべきだと私は考えています。定型メールの作成や社内文書の下書きなど、小さな部分からでも生成AIによる業務改善は始められますので、ぜひ試してみていただきたいと思います。
記事にもあるように、大切なのは、期待しすぎず、うまく役割を分担すること。
AIは「魔法」ではなく、あくまでも「道具」として使える「術」を社内に蓄えていくことがポイントです。
地方・中小企業の方はぜひご一読いただきたい記事です。Check it!
生成AIとうまく付き合うコツ
コンクラーベから万博トイレまで…生成AIの答え信じて大丈夫?(NHK)
記事では、生成AIによる誤情報の問題について、複数の実例を通じて紹介されています。
たとえば「根比べの語源がコンクラーベ」とする誤情報や、「大阪万博のトイレがくみ取り式」といった誤った内容が、生成AIによって拡散されたケースが報告されています。
特に注目すべきは、生成AIが“知らないことでも答えてしまうという性質。
海外では無実の人が殺人犯として名前を出されたり、弁護士が実在しない判例を裁判に提出して制裁を受けたケースまで起きているとのこと。
これら「誤情報が出力される」ことに対して、記事では、生成AIとうまく付き合うコツとして次のようにまとめられています。
- AIにわかりやすく質問するなど、コミュニケーションを増やすこと
- 1つのAIだけでなく、ほかのAIにも聞いてみること
- AIが回答の根拠とした一次情報や引用元を確認すること
誤情報が出力されるとはいえ、もはや、生成AIを利用しないということは考えられません。これは地方の中小企業にとっても同じことです。
生成AIの便利さとリスクを実例から学べる記事ですので、ぜひご一読ください。Check it!
AI検索は「順位」よりも「Retrieval」
この記事では、AIによる検索が主流になりつつある中で、従来の「順位」を追いかけるSEOではなく、「AIに拾われるかどうか」が重要になっていることが紹介されています。
特に注目すべきは、「リトリーバル=取り出しやすさ」が決め手になっているという点です。
AIは順位ではなく、「今の質問に合った答え」を探して表示します。そのため、情報は明確に、簡潔に、そして質問と同じ言葉で書かれている必要があります。
地方の中小企業にとっても、これは他人事ではありません。
これからのウェブページやブログ記事は、「検索順位で上に出す」のではなく、「AIが引用しやすい形で伝える」ことが(も)求められるからです。見出しを明確にし、答えを前に出す、わかりやすい言葉で書く――そうしたことが、今後ますます重要になりそうです。
この変化はとてつもなく大きいことですが、まだ世界中が手探りの状態です。
かなり専門的、かつ英文の記事ですが、AI時代のSEOの本質が詰まった記事ですのでご興味ある方はぜひご一読ください。Check it!
次回をお楽しみに!
こちらの記事もおすすめ!
ネット活用のヒントを配信中!
ネット活用のヒントを check!!
- 地方・中小企業の皆様 …… 今、目の前にあるチャンス! & 売れる仕組み作り
- 自治体サイト担当者様 …… 自治体ホームページの課題と可能性を知る
- 観光に関わる皆様 …… ネット活用の "もったいない!" 事例を紹介