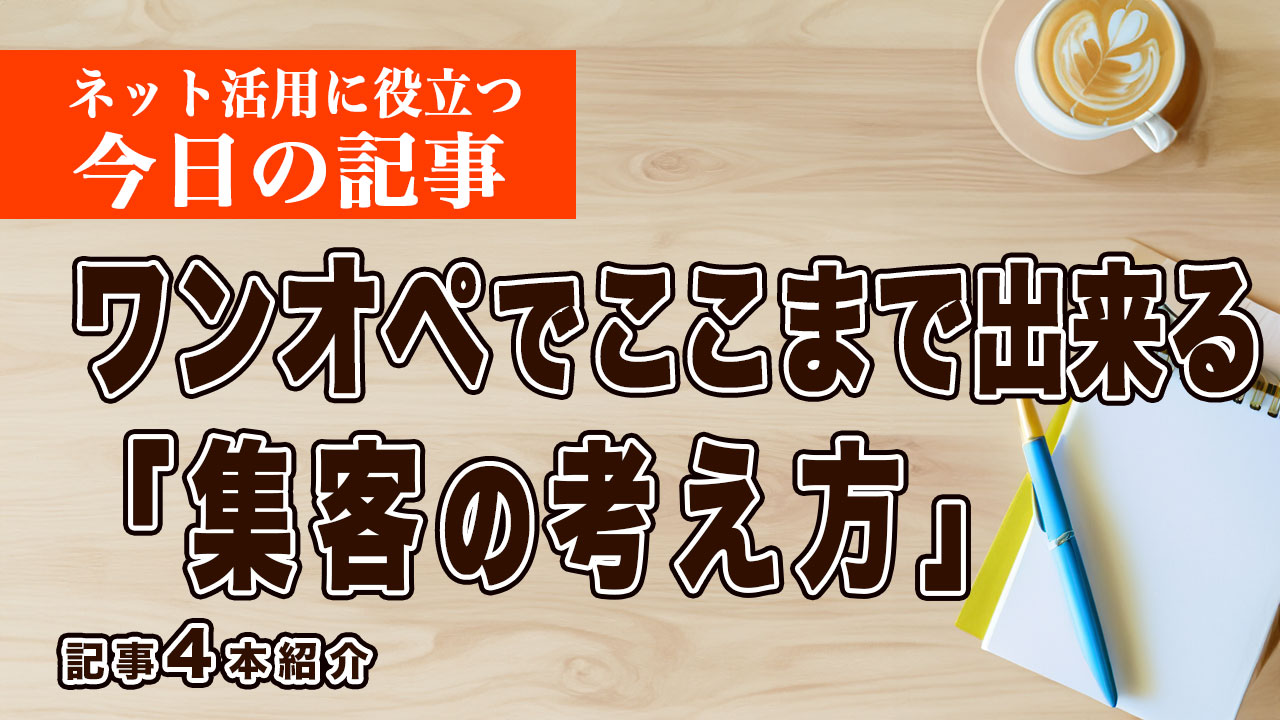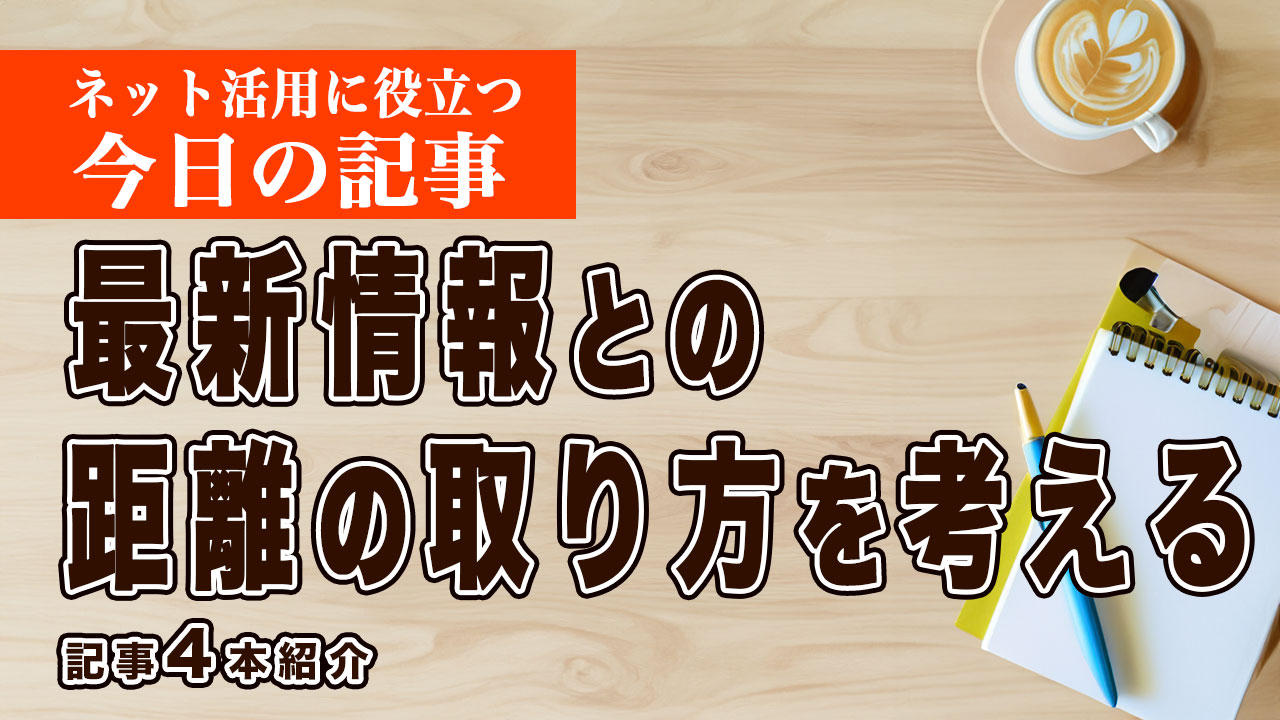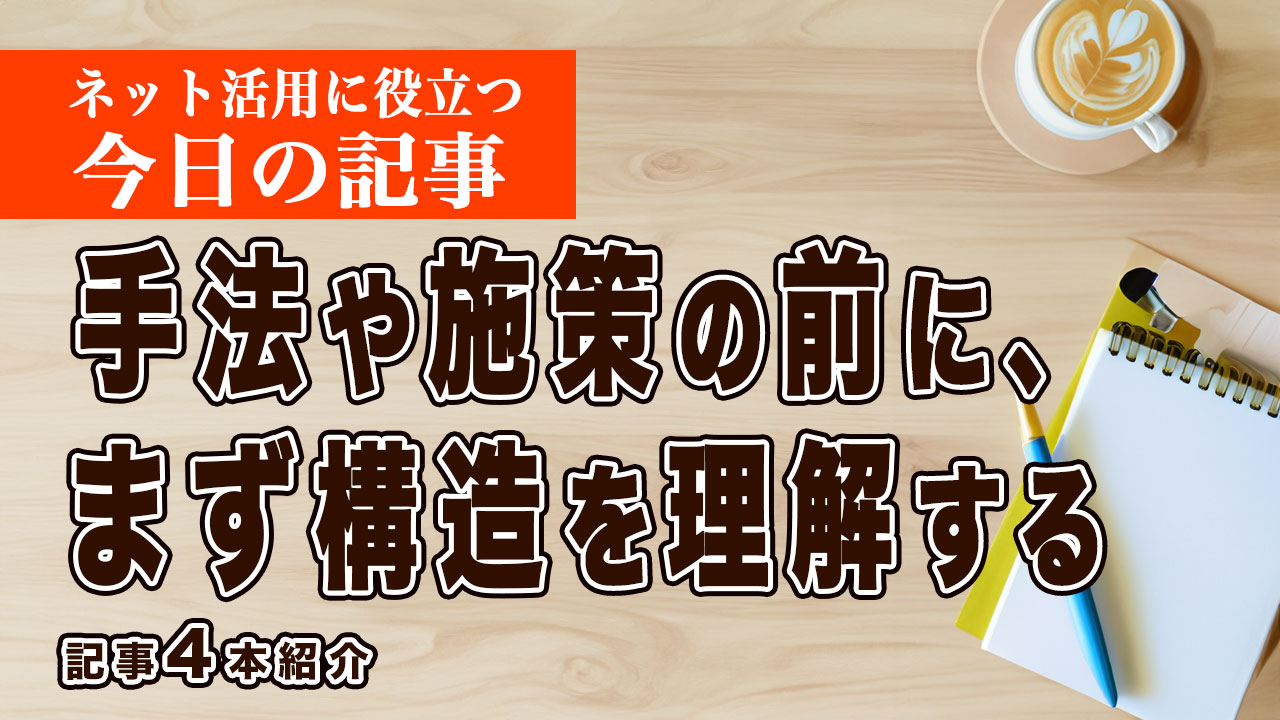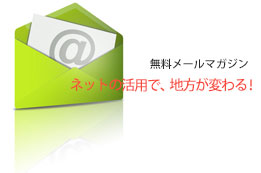地方や中小企業の情報発信に役立つ記事をピックアップして紹介しています。
みなさんの仕事の現場でお役立てください
今回は以下の4本です
- アルゴリズムの変遷とSNSへの影響
- 会社でのSNS運用ポイント
- 「AI検索」時代のSEO
- 東南アジアのTikTokを知る
アルゴリズムの変遷とSNSへの影響
アルゴリズムの「発展と影響」 現代のSNSマーケをどう変える?(ITmedia)
「情報発信」という言葉を頻繁に利用しますが、ネットにおける情報発信を考えた時、私たちの情報発信は大手IT企業のアルゴリズムに支配されるゲームの中での行為にすぎません。ゲームのルールが変わればそれに私たちの情報発信も影響されることになり、時に右往左往することになります。今回取り上げている記事では、このルール変更によってSNSがどう変わったのかが紹介されています。
当初、SNSは「知り合い」や「つながりたい人」(=フォロワー)からの投稿がタイムラインに並ぶという形でスタートしました。この知り合いやフォロワーの網目は「ソーシャル・ネットワーク」とよばれ、リアルの世界ではつながりがあってもそれが可視化されることもありませんでしたか、世界で唯一、Faceobook がこのソーシャルネットワーク(=世界中の人間関係を)をおさえており、莫大なビジネスの可能性を秘めていると言われていました。またFacebookによる「タイムライン」という表示形態の発明は、SNS以前ではそれぞれの人の場所(ブログであったり掲示板であったり)に個別に見に行かないといけなかったものが、1カ所でそれを見ることができる画期的なものとして受け取られていました。いずれにしても、当時のSNSは、「知り合い」や「つながりたい人」の情報が自分の目の前に常に流れてくるというものでした。
現在のSNSは、すでに皆さんがあらゆるSNSで体験されているように、知り合いでもないまったく見ず知らずの人の投稿、時に「どうしてこの動画が表紙されるの!?」と思われるような投稿までもが、いや、そのような投稿がメインに表示されるようになっています。
記事ではこれを「アルゴリズムの発展」として、"「共感」から「注目」へ" という表現で解説してくれています。記事にはありませんが、このアルゴリズムの変更は TikTok の台頭によって他のSNSが進めてきたものなのです。そのような前提を踏まえて、大きな視点でソーシャルメディアの現在の立ち位置をぜひご覧ください。Check it!
会社でのSNS運用ポイント
SNS運用は運用チームづくりが全て!求められるスキルセットとマインドセットとは(アドタイ)
個人でSNSを自由に行うのと、会社がある目的に向けてSNSを運用するのとでは、その考え方が大きく異なります。SNSに詳しそうなスタッフ個人に任せるという単純な方法で運用するわけにはいきません。記事では、ある目的に向けてチームでSNSを運用するためのポイントはどこにあるのかが紹介されています。ぜひ参考にしてみてください。Check it!
「AI検索」時代のSEO
searchGPT や perplexity などの「AI検索」の台頭は、私たちに大きな影響をおよぼします。検索という行為は、我々企業にとって「自社に興味をもってくれるかもしれない、まだ見ぬお客様」と出会う場、と位置付けることができます。この「場」が、かつては検索が主流だったものからSNSや動画メディアも加わるようになり、そして今、検索という場そのものにも大きな変化が訪れようとしています。
これまでの検索という行為は、「知りたいことが掲載されているページを調べる」という行為でした。そのため企業は、「知りたいこと」をページの内容として掲載することで「まだ見ぬお客様」との出会いの場を作り上げようとしてきました。これがいわゆる、コンテンツマーケティングと言われるものです。
しかし、AI検索はこれをひっくり返す可能性があります。AI検索は「知りたいことが掲載されているページ」を表示する代わりに、AI側で解釈して「知りたいことの回答」をダイレクトに表示するからです。そのため perplexity は自らを、検索エンジンではなく「回答エンジン」だと表現しています。知りたいことの回答が検索結果画面に直接表示されることは、利用するユーザーにとってはとても便利な体験ではありますが、これまで、検索→サイトへの訪問という形で「まだ見ぬお客様との出会いの場」を重視していた企業にとっては大きな痛手となります。これまでのようにサイトに訪問せずとも回答が得られるわけですから、その先のサイトに行く必要がない、というのが理由です。このことを「ゼロクリック」と呼びますが、この記事でも紹介されているように、2026年までに検索量そものもが25%減少、検索からのトラフィックは50%減少すると予測されています。
では企業はどのような対応をすればいいのか、が今回紹介している記事の内容です。これまでの SEO に変わる「生成エンジン最適化」(GEO)という考え方も紹介されています。
まだ誰にも答えはわかりませんし、「まだ見ぬお客様との出会いの場」を検索以外の場所に求めた方がビジネス的には効果が高い可能性すらあります。
具体的なことはともかく、少なくとも今起きていく大きな変化と、その先にどのような可能が示唆されているのかをぜひご覧いただければと思います。英文の記事ですので翻訳機能を利用としてどうぞ。Check it!
東南アジアのTikTokを知る
日本と「全然違う」東南アジアEC事情、TikTokの「ある機能」が大人気のワケ(ビジネス+IT)
日本よりも圧倒的に若者が多く、日本よりも圧倒的にTikTokが利用されている東南アジアの様子が紹介されています。詳しくは記事を読んでいただいた方がいいのですが、日本と異なる利用や違う景色を見ると新しいヒントがありますので、ぜひ参考になさってください。
また、記事にもありますが TikTok の各国の利用状況がこちらで紹介されています。合わせてCheck it!
次回をお楽しみに!
こちらの記事もおすすめ!
ネット活用のヒントを配信中!
ネット活用のヒントを check!!
- 地方・中小企業の皆様 …… 今、目の前にあるチャンス! & 売れる仕組み作り
- 自治体サイト担当者様 …… 自治体ホームページの課題と可能性を知る
- 観光に関わる皆様 …… ネット活用の "もったいない!" 事例を紹介